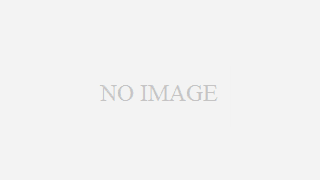 未分類
未分類 摩擦レス洗顔で透明感アップ!EKATO 炭酸泡パック洗顔を1ヶ月使ってみた結果
【1分で透明肌】EKATO 炭酸泡パック洗顔を実際に使ってレビュー!摩擦レスで毛穴汚れをスッキリ落とし、くすみ・むくみをケア。忙しい朝でもエステ級の洗い上がりを叶える炭酸泡洗顔。初回43%OFFキャンペーン実施中!
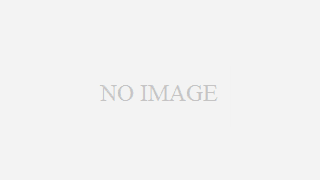 未分類
未分類  未分類
未分類  未分類
未分類 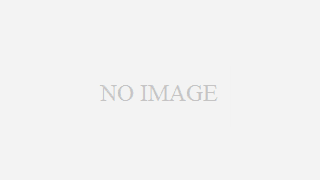 未分類
未分類  未分類
未分類  未分類
未分類  未分類
未分類  未分類
未分類  未分類
未分類  未分類
未分類