一 お話のはじまり

コペンハーゲンで、そこの東通の、王立新市場からとおくない一軒の家は、たいそうおおぜいのお客でにぎわっていました。人と人とのおつきあいでは、ときおりこちらからお客をしておけば、そのうち、こちらもお客によばれるといったものでしてね。お客の半分はとうにカルタ卓《づくえ》にむかっていました。あとの半分は、主人役の奥さんから、今しがた出た、
「さあ、こんどはなにがはじまりしましょうね。」というごあいさつが、どんな結果になってあらわれるかと、手ぐすねひいて、待っているのです。もうずいぶんお客さま同士の話がはずむだけはずんでいました。そういう話のなかには、中世紀時代の話もでました。あるひとりは、あの時代は今の時代にくらべては、くらべものにならないほどよかったと主張しました。じっさい司法参事官《しほうさんじかん》のクナップ氏などは、この主張《しゅうちょう》にとても熱心で、さっそく主人役の奥さんを身方につけてしまったほどでした。そうしてこのふたりは*エールステッドが年報誌上にかいた古近代論の、現代びいきな説にたいして、やかましい攻撃をはじめかけたくらいです。司法参事官の説にしたがえば、デンマルクの**ハンス王時代といえば、人間はじまって以来、いちばんりっぱな、幸福な時代であったというのでした。
[#ここから5字下げ]
*デンマルクの名高い物理学者(一七七七―一八五一)。
**ヨハン二世(一四八一―一五一三)。選挙侯エルンスト・フォン・ザクセンのむすめクリスティーネと婚。ノルウェイ・スエーデン王を兼ねた。
[#ここで字下げ終わり]
さて会話は、こんなことで、賛否《さんぴ》こもごも花が咲いて、あいだに配達の夕刊がとどいたので、ちょっと話がとぎれたぐらいのことでした。でも、新聞にはべつだんおもしろいこともありませんでしたから、話はそれなりまたつづきました。で、わたしたちはちょっと表の控間へはいってみましょう。そこにはがいとうと、つえと、かさと、くつの上にはうわおいぐつが一足《いっそく》置いてありました。みるとふたりの婦人が卓《つくえ》のまえにすわっていました。ひとりはまだ若い婦人ですが、ひとりは年をとっていました。ちょっとみると、お客のなかのお年よりのお嬢さん、または未亡人《びぼうじん》の奥さんのお迎えに来て、待っている女中かとおもうでしょう。でもよくみると、ふたりとも、ただの女中などでないということはわかりました。それにはふたりともきゃしゃすぎる手をしていましたし、ようすでも、ものごしでも、りっぱすぎていましたが、着物のしたて方にしても、ずいぶんかわっていました。ほんとうは、このふたりは妖女《ようじょ》だったのです。若いほうは幸福の女神でこそありませんが、そのおそばづかえのそのまた召使のひとりで、ちょいとしたちいさな幸福のおくりものをはこぶ役をつとめているのです。年をとったほうは、だいぶむずかしい顔をしていました。これは心配の妖女でした。このほうはいつもごじしん堂堂《どうどう》と、どこへでも乗り込んでいってしごとをします。すると、やはりそれがいちばんうまくいくことを知ってました。
ふたりはおたがいに、きょうどこでなにをして来たか話し合っていました。幸福の女神のおそばづかえのそのまた召使は、ほんのふたつ三つごくつまらないことをして来ました。たとえば買い立ての帽子が夕立にあうところを助けてやったり、ある正直な男に無名の篤志家《とくしか》からほどこし物をもらってやったり、まあそんなことでした。しかし、そのあとで、もうひとつ、話しのこしていたことは、いくらかかわったことであったのです。
「まあついでだからいいますがね。」と、幸福のおそばづかえのそのまた召使は話しました。「きょうはわたしの誕生日《たんじょうび》なのですよ。それでそのお祝いに、ご主人からうわおいぐつを一足《いっそく》あずけられました。そしてそれを人間のなかま[#「なかま」は底本では「なまか」]にやってくれというのです。そのうわおいぐつにはひとつの徳《とく》があって、それをはいたものはたちまち、だれでもじぶんがいちばん住んでみたいとおもう時代なり場所なりへ、はこんで行ってもらえて、その時代なり場所なりについて、のぞんでいたことがさっそくにかなうのです。そういうわけで、人間もどうやら、この世の中ながら幸福になれるのでしょう。」
こういうと心配の妖女《ようじょ》が、
「いや、お待ちなさいよ。そのうわおいぐつをはいた人は、きっとずいぶんふしあわせになるでしょうよ。そしてまた、はやくそれをぬぎたいとあせるようになるでしょうよ。」といいました。
「まあそこまではおもわなくても。」と、もうひとりがふふくらしくいいました。「さあ、それでは幸福のうわおいぐつを、ここの戸口におきますよ。だれかがまちがってひっかけていって、いやでも、すぐと幸福な人間になるでしょう。」
どうです。これがふたりの女の話でした。
二 参事官はどうしたか

もうだいぶ夜がふけていました。司法参事《しほうさんじ》官クナップ氏は、ハンス王時代のことに心をとられながら、うちへかえろうとしました。ところで運命の神さまは、この人がじぶんのとまちがえて、幸福のうわおいぐつをはくように取りはからってしまいました。そこで参事官がなんの気なしにそれをはいたまま東通へ出ますと、もうすぐと、うわおいぐつの効能があらわれて、クナップ氏はたちまち三百五十年前のハンス王時代にまでひきもどされてしまいました。さっそくに参事官は往来のぬかるみのなかへ、両足つっこんでしまいました。なぜならその時代はもちろん昔のことで、石をしいた歩道なんて、ひとつだってあるはずがないのです。
「やれやれ、これはえらいぞ、いやはや、なんというきたない町だ。」と参事官がいいました。「どうして歩道をみんな、なくしてしまったのだろう。街灯《がいとう》をみんな消してしまったのだろう。」
月はまだそう高くはのぼっていませんでしたし、おまけに空気はかなり重たくて、なんということなしに、そこらの物がくらやみのなかへとろけ出しているようにおもわれました。次の横町の角《かど》には、うすぐらい灯明がひとつ、聖母のお像のまえにさがっていましたが、そのあかりはまるでないのも同様でした。すぐその下にたって、仰いでみてやっと、聖母と神子《しんじ》の彩色した像が分かるくらいでした。
「これはきっと美術品を売る家なのだな。日がくれたのに看板をひっこめるを忘れているのだ。」と、参事官はおもいました。
むかしの服装をした人がふたり、すぐそばを通っていきました。
「おや、なんというふうをしているのだ。仮装舞踏会《かそうぶとうかい》からかえって来た人たちかな。」と、参事官は、ひとりごとをいいました。
ふとだしぬけに、太皷と笛の音《ね》がきこえて、たいまつがあかあかかがやき出しました。参事官はびっくりしてたちどまりますと、そのとき奇妙な行列が鼻のさきを通っていきました。まっさきには皷手の一隊が、いかにもおもしろそうに太皷を打ちながら進んで来ました。そのあとには、長い弓と石弓をかついだ随兵《ずいひょう》がつづきました。この行列のなかでいちばんえらそうな人は坊さんの殿様でした。びっくりした参事官は、いったいこれはいつごろの風をしているので、このすいきょうらしい仮装行列をやってあるく人はたれなのだろう、といって、行列のなかの人にたずねました。
「シェランの大|僧正《そうじょう》さまです。」と、たれかがこたえました。
「大僧正のおもいつきだと、とんでもないことだ。」と、参事官はため息をついてあたまを振りました。そんな大僧正なんてあるものか。ひとりで不服をとなえながら、右も左もみかえらずに、参事官はずんずん東通をとおりぬけて、高橋広場《たかばしひろば》にでました。ところが宮城広場へ出る大きな橋がみつかりません。やっとあさい小川をみつけてその岸に出ました。そのうち小舟にのってやって来るふたりの船頭らしい若者にであいました。
「島《ホルメン》へ渡りなさるのかな。」と、船頭はいいました。
「島《ホルメン》へ渡るかって。」と、参事官はおうむ返しにこたえました。なにしろ、この人はまた、じぶんが今、いつの時代に居るのか、はっきり知らなかったのです。
「わたしは、クリスティアンス ハウンから小市場通へいくのだよ。」
こういうと、こんどはむこうがおどろいて顔をみました。
「ぜんたい橋はどこになっているのだ。」と参事官はいいました。「第一ここにあかりをつけておかないなんてけしからんじゃないか。それにこのへんはまるで沼の中をあるくようなひどいぬかるみだな。」
こんなふうに話しても、話せば話すほど船頭にはよけいわからなくなりました。
「どうもおまえたちの*ボルンホルムことばは、さっぱりわからんぞ。」と、参事官はかんしゃくをおこしてどなりつけました。そして背中をむけてどんどんあるきだしました。
[#ここから5字下げ]
*バルティック海上の島。島の方言がかわっていた。
[#ここで字下げ終わり]
しかしいくらあるいても、参事は橋をみつけることはできませんでした。らんかんらしいものはまるでありませんでした。
「どうもこのへんは実にひどい所だ。」と、参事官はいいました。じぶんのいる時代を、この晩ほどなさけなくおもったことはありませんでした。「まあこのぶんでは、辻馬車をやとうのがいちばんよさそうだ。」と、参事官はおもいました。そういったところで、さて、どこにその辻馬車があるでしょうか。それは一台だってみあたりそうにはありませんでした。
「これではやはり、王立新市場までもどるほうがいいだろう。あそこならたくさん馬車も来ているだろう。そうでもしないと、とてもクリスティアンス ハウンまでかえることなどできそうもない。」
そこで、またもどって、東通のほうへあるきだしました。そしてほとんどそこを通りぬけようとしたときに、たかだかと月がのぼりました。
「おや、なんとおもって足場みたいなものをここに建てたのだ。」
東門をみつけて、参事官はこうさけびました。そのころ東通のはずれに、門があったのです。
とにかく、出口をさがして、そこをとおりぬけると、今の王立新市場のある通へでました。けれどそれはただのだだっ広い草原でした。二三軒みすぼらしいオランダ船の船員のとまる下宿の木小屋《きごや》が、そのむこう岸に建っていて、オランダッ原《ぱら》ともよばれていた所です。
「おれはしんきろう[#「しんきろう」に傍点]をみているのか知らん。それとも酔っぱらっているのじゃないか知ら。」と、参事は泣き声をだしました。「とにかくありゃあなんだ。」
もうどうしても、病気にかかっているにちがいない、そうおもい込んで、また引っかえしました。往来をとぼとぼあるきあるき、なおよくそこらの家のようすをみると、たいていの家は木組の小屋で、なかにはわら屋根の家もありました。
「いや、どうもへんな気分でしょうがない。」と、参事官はため息をつきました。「しかしおれは、ほんの一杯ポンスを飲んだだけだが、それがうまくおさまらないとみえる。それに、時候はずれのむしざけ[#「ざけ」に傍点]をだしたりなんかして、まったくくいあわせがわるかった。もういちどもどっていって、主人の代理公使夫人に小言《こごと》をいって来ようかしらん。いや、それもばからしいようだ。それにまだ起きているかどうかわからない。」
そういいながら、その家の方角をさがしましたが、どうしてもみつかりませんでした。
「どうもひどいことだ。東通がまるでわからなくなった。一軒の店もみえはしない。みすぼらしいたおれかけの小屋がみえるだけだ。これではまるでリョースキレか、リンステッドへでもいったようだ。ああ、おれは病気だぞ。遠慮をしているところでない。だが、いったい代理公使の家はどこなんだろう。どうしてももうもととはちがっている。しかもなかには人がまだ起きている。――どうしてもおれは病気だ。」
そのとき参事官は、一軒戸のあいている家の前へ出ました。すきまからあかりが往来へさしていました。これはそのころの安宿で、半分居酒屋のようなものでした。ところで、そのなかはホルシュタイン風の百姓家の台所といったていさいでした。なかにはおおぜいの人間が、船乗や、コペンハーゲンの町人や二三人の本読《ほんよみ》もまじって、みんなビールのジョッキをひかえて、むちゅうになってしゃべっていて、はいって来た客にはいっこう気がつかないようでした。
参事官はお客をむかえにたったおかみさんにいいました。「お気のどくですが、わたしは非常にぐあいがわるいのです。クリスティアンスハウンまで、辻馬車をやとってはもらえませんか。」
おかみさんは、参事官の顔をうさんらしくみて首をふりました。それからドイツ語で話しかけました。参事官はそれで、おかみさんがデンマルク語を知らないことがわかったので、こんどはドイツ語で同じ註文をくり返しました。その言葉と服装から、おかみさんは、この客をてっきり外国人だとおもい込みました。で、気分のわるそうなようすをみると、さっそく水をジョッキに一杯ついでもって来ました。水はなんだかしょっぱいへんな味がしました。そのくせ外の噴井戸《ふきいど》から汲んで来たのです。
参事官は両手であたまをおさえて、ふかいためいきをつきながら、いまし方つづいておこった奇妙なことを、あれこれとおもいめぐらしていました。
「それはきょうの*『ダーエン』ですか。」と、参事官は、おかみさんがもっていきかけた大きな紙をみて、ほんのおせじにききました。
[#ここから5字下げ]
*コペンハーゲン発行の夕刊新聞。一八〇五―四三。
[#ここで字下げ終わり]
お上さんは、なにを客がいうのだかわかりませんでしたから、だまってその紙を渡しました。それはむかし、キョルンの町にあらわれたふしぎな空中|現象《げんしょう》をかいた一枚の木版刷《もくはんずり》でした。
「こりゃなかなか古い。」と参事官は、あんがいな掘り出しもので、おおきに愉快になりました。
「おまえさん、このめずらしい刷物《すりなの》をどうして手に入れたのだね。こりゃなかなかおもしろいものだよ。もっとも話はまるっきりおとぎばなしだがね。今日では、これに類した空中現象は、北極光をみあやまったものだということになつている。おそらく電気の作用でおこるものらしい。」
すると参事官のすぐそばにすわって、この話をきいた人たちが、びっくりしてその顔をながめました。そして、そのうちのひとりは、たち上がって、うやうやしく帽子をぬいで、ひどくしかつめらしく「先生、どうも、あなたはたいそうな学者でおいでになりますな。」といいました。
「いやはや、どういたしまして。」と、参事官は答えました。「ついだれでも知っているはずのことをふたことみこと、お話しただけですよ。」
「けんそんは美徳で。」とその男はラテン語まじりにいいました。「[#「「」は底本では欠落]もっともお説にたいして、わたくしは異説をさしはさむものであります。しかしながら、わたくしの批判はしばらく保留いたしましよう。」
「失礼ながら、あなたはどなたですか。」と、参事官がたずねました。
「わたくしは聖書得業士でして。」と、その男が答えました。
その答で参事官は十分でした。その人の称号と服装はそれによくつりあっていました。多分、これは村の老先生というやつにちがいない。よくユラン(ユットランド)地方でみかけるかわりものだと参事官はおもいました。
「ここはいかにも学者清談の郷ではありませんな。」と、その男はつづけていいだしました。「しかしどうかまげてお話しください。あなたはむろん、古書はふかくご渉猟《しょうりょう》でしょうな。」
「はい、はい、それはな。」と、参事官は受けて、「わたしも有益な古書を読むことは大好きですが、とうせつの本もずいぶん読みます。ただ困るのは『その日、その日の話』というやつで、わざわざ本でよまないでも、毎日のことで飽き飽きしますよ。」
「[#「「」は底本では「『」]『その日、その日の話』といいますと。」と、得業士はふしんそうにききました。
「いや、わたしのいうのは、このごろはやる新作の小説のことですよ。」
「ははあ。」と、得業士はにっこりしながら、「あれもなかなか気のきいたものでして、宮中ではずいぶん読まれていますよ。*王様はとりわけ、アーサー王と円卓《えんたく》の騎士の話を書いた、イフヴェンとゴーディアンの物語を好いていられます。それでご家来の人達とあの話をして興《きょう》がっていられます。」
[#ここから5字下げ]
*デンマルクの詩人ホルベルのデンマルク国史物語に、ハンス王が寵臣のオットー ルードとアーサー王君臣の交りについてとんち問答した話がかいてある。なお、「その日その日の物語」は、文士ハイベルの母のかきのこした身の上話。
[#ここで字下げ終わり]
「それはまだ読んでいません。」と、参事官はいいました。「ハイベルが出した新刊の本にちがいありませんね。」
「いや、ハイベルではありません。ゴットフレト フォン ゲーメンが出したのです。」と、学士は答えました。
「へへえ、その人は作者ですか。」と、参事官がたずねました。「ゴットフレト フォン ゲーメンといえば、すいぶん古い名まえですね。あれはなんでも、ハンス王時代、デンマルクで印刷業をはじめた人ではありませんか。」
「そうですとも。この国でははじめての印刷屋さんですよ。」と、学士が答えました。
ここまではどうにかうまくいきました。こんどは町人のひとりが、三年まえ流行した伝染病の話をしだしました。ただそれは一四八四年の話でした。参事官はそれを一八三〇年代はやったコレラの話をしているのだとおもいました。そこで会話は、どうにかつじつまがあいました。一四九〇年の海賊戦争もつい近頃のことでしたから、これも話題にのぼらずにいませんでした。で、イギリスの海賊船が、やはり同じ波止場か船をりゃくだつしていった、とその男は話しました。ところで、*一八〇一年の事件をよく知っている参事官は、進んでその話に調子をあわせて、イギリス人に攻撃をしかけました。これだけはまずよかったが、そのあとの話はそううまくばつがあいませんでした。ひとつひとつに話がくいちがいました。学士先生は気のどくなほどなにも知りませんでした。参事官のごくかるく口にしたことまでが、いかにもでたらめな、気ちがいじみた話にきこえました。そうなると、ふたりはだまって顔ばかりみあわせました。いよいよいけないとなると、学士はいくらか相手にわからせることができるかとおもって、ラテン語で話しましたけれど、いっこう役には立ちませんでした。
[#ここから5字下げ]
*一八〇一年四月二日英艦の攻撃事件。
[#ここで字下げ終わり]
「あなた、ご気分はどうですね。」と、おかみさんはいって、参事官のそでをひっぱりました。
ここではじめて、参事官はわれにかえりました。話でむちゅうになっているあいだは、これまでのことをいっさい忘れていたのです。
「やあ、たいへん、わたしはどこにいるのだ。」と、参事官はいって、それをおもいだしたとたん、くらくらとなったようでした。
「さあ、クラレットをやろうよ。蜜酒に、ブレーメン・ビールだ。」と、客のひとりがさけびました。
「どうです、いっしょにやりたまえ。」
ふたりの給仕のむすめがはいって来ました。そのひとりは*[#「*」は底本では欠落]ふた色の染分け帽子をかぶって来ました。ふたりはお酒をついでまわって、おじぎをしました。参事官はからだじゅうぞっとさむけがするようにおもいました。
[#ここから5字下げ]
*ハンス王時代下等な酌女のしるし。
[#ここで字下げ終わり]
「やあ、こりゃなんだ。こりゃなんだ。」と、参事官はさけびました。けれども、いやでもいっしょに飲まなければなりませんでした。客どもはごくたくみにこの紳士《しんし》をあつかいました。参事官はがっかりしきっていました。たれか、「あの男酔っぱらっているよ。」といったものがありましたが、そのことばをうそだとおこるどころではありません。どうぞ、ドロシュケ(辻馬車)を一台たのむといったのが精いっぱいでした。ところがみんなはそれをロシア語でも話しているのかとおもいました。
参事官は、これまでこんな下等な乱暴ななかまにはいったことはありませんでした。
「これではまるで、デンマルクの国が、異教国の昔にかえったようだ。こんなおそろしい目にあったことははじめてだぞ。」と、参事官はおもいました。しかしそのときふとおもいついて、参事官はテーブルの下にもぐりこんで、そこから戸口の所まではい出そうとしました。そのとおりうまくやって、ちょうど出口までいったところを、ほかの者にみつけられました。みんなは参事官の足をとって引きもどしました。そのとき大仕合わせなことには、うわおおいぐつがすっぽりぬけました。――それでいっさいの魔法が消えてなくなりました。
そのとき参事官ははっきりと、すぐ目のまえに、街灯がひとつ、かんかんともっていて、そのうしろに大きな建物の立っているのをみつけました。そこらじゅうみまわしても、おなじみのあるものばかりでした。それは、今の世の中で毎日みているとおりの東通でした。参事官は玄関の戸に足をむけて腹ンばいになっていたのです。すぐむこうには町の夜番が、すわって寝込んでいました。
「やあたいへん、おれは往来で寝て、夢をみていたのか。」と、参事官はさけびました。「なるほど、これは東通だわい。どうもなにかが、かんかんあかるくって、にぎやかだな。それにしてもいっぱいのポンスのききめはじつにおそろしい。」
それから二分ののち参事官は、ゆうゆうと辻馬車のなかにすわって、クリスティアンス ハウンのじぶんの家のほうへはこばれて[#「はこばれて」は底本では「はこぱれて」]いきました。参事官はいましがたさんざんおそろしい目や心配な目にあったことをおもいだすと、今の世の中には、それはいろいろわるいことはあっても、ついさっきもっていかれた昔の時代よりはずっとましだということをさとりました。どうですね、参事官は、もののわかったひとでしょう。
三 夜番のぼうけん

「おやおや、あすこにうわおいぐつが一足ころがっている。」と夜番はいいました。「きっとむこうの二階にいる中尉さんの物にちがいない。すぐ門口にころがっているから。」
正直な夜番は、ベルをならして、うわおいぐつを持主にわたそうとおもいました。二階にはまだあかりがついていました。けれど、うちのなかのほかの人たちまでおどろかすのも気のどくだとおもったので、そのままにしておきました。
「だが、こういうものをはいたら、ずいぶん温かいだろうな。」と、夜番はひとりごとをいいました。「なんて上等なやわらかい革がつかってあるのだろう。」うわおいぐつはぴったり夜番の足にあいました。「どうも、世の中はおかしなものだ。いまごろ中尉さんは、あの温かい寝床のなかで横になっていればいられるはすなのだ。ところが、そうでない。へやのなかをいったり来たり、あるいている。ありゃしあわせなお人さな。おかみさんもこどももなくて、毎晩、夜会にでかけていく。おれがあの人だったらずいぶんしあわせな人間だろうな。」
夜番がこういって、こころのねがいを口にだしますと、はいていたうわおいぐつはみるみる効能をあらわして、夜番のたましいはするすると中尉のからだとこころのなかへ運んで持っていかれました。
そこで夜番は、二階のへやにはいって、ちいさなばら色の紙を指のまたにはさんで持ちました。それには詩が、中尉君自作の詩が書いてありました。それはどんな人だって、一生にいちどは心のなかを歌にうたいたい気持になるおりがあるもので、そういうとき、おもったとおりを紙に書けば[#「書けば」は底本では「書けは」]、詩になります。そこで紙にはこう書いてありました。
「ああ、金持でありたいな。」
「ああ、金持でありたいな。」おれはたびたびそうおもった。
やっと二尺のがきのとき、おれはいろんな望をおこした。
ああ、金持でありたいな――そうして士官になろうとした、
サーベルさげて、軍服すがたに、負革《おいかわ》かけて。
時節がくると、おれも士官になりすました。
さてはや、いっこう金《かね》はできない。なさけないやつ。
全能の神さま、お助けください。
ある晩、元気で浮かれていると、
ちいさい女の子がキスしてくれた、
おとぎ歌なら、持ちあわせは山ほど、
そのくせ金にはいつでも貧乏――
こどもは歌さえあればかまわぬ。
歌なら、山ほど、金には、いつもなさけないやつ。
全能の神さま、ごらんのとおり。「ああ、金持でありたいな。」おいのりがこうきこえだす。
こどもはみるみるむすめになった、
りこうで、きれいで、心もやさしいむすめになった。
ああ、分らせたい、おれの心のうちにある――
それこそ大したおとぎ話を――むすめがやさしい心をみせりゃ。
だが金はなし、口には出せぬ。なさけないやつ。
全能の神さま、おこころしだいに。ああ、せめてかわりに、休息と慰安《なぐさめ》、それでもほしい。
そうすりゃなにも心の悩み、紙にかくにもあたらない。
おれの心をささげたおまえだ、わかってもくれよ。
若いおもい出つづった歌だ、読んでもくれよ。
だめだ、やっぱりこのままくらい夜《よる》にささげてしまうがましか。
未来はやみだ、いやはやなさけないやつめ。
全能の神さま、おめぐみください。
そうです、人は恋をしているときこんな詩をつくります。でも用心ぶかい人は、そんなものを印刷したりしないものです。中尉と恋と貧乏、これが三角の形です。それとも幸福のさいころのこわれた半かけとでもいいましようか。それを中尉はつくづくおもっていました。そこで、窓わくにあたまをおしつけて、ふかいため息ばかりついていました。
「あすこの往来にねている貧しい夜番のほうが、おれよりはずっと幸福だ。あの男にはおれのおもっているような不足というものがない。家もあり、かみさんもあり、こどももあって、あの男のかなしいことには泣いてくれ、うれしいことには喜んでくれる。ああ、おれはいっそあの男と代ることができたら、今よりずっと幸福になれるのだがな。あの男はおれよりずっと幸福なのだからな。」
中尉がこうひとりごとをいうと、そのしゅんかん、夜番はまたもとの夜番になりました。なぜなら幸福のうわおいぐつのおかげで、夜番のたましいは中尉のからだを借りたのですけれど、その中尉は、夜番よりもいっそう不平家で、おれはもとの夜番になりたいとのぞんだのでした。そこで、そのおのぞみどおり、夜番はまた夜番になってしまったのです。
「いやな夢だった。」と、夜番はいいました。「が、ずいぶんばかばかしかった。おれはむこう二階の中尉さんになったようにおもったが、まるで愉快でもなんでもなかった。息のつまるほどほおずりしようとまちかまえていてくれる、かみさんやこどものいることを忘れてなるものか。」
夜番はまたすわって、こくりこくりやっていました。夢がまだはっきりはなれずにいました。うわおいぐつはまだ足にはまっていました。そのとき流れ星がひとつ、空をすべって落ちました。
「ほう、星がとんだ。」と、夜番はいいました。「だが、いくらとんでも、あとにはたくさん星がのこっている。どうかして、もう少し星のそばによってみたいものだ。とりわけ月の正体をみてみたいものだ。あれだけはどんなことがあっても、ただの星とちがって、手の下からすべって消えていくということはないからな。うちのかみさんがせんたく物をしてやっている学生の話では、おれたちは死ぬと、星から星へとぶのだそうだ。それはうそだが、しかしずいぶんおもしろい話だとおもう。どうかしておれも星の世界までちょいととんでいくくふうはないかしら、すると、からだぐらいはこの段段のうえにのこしていってもいい。」
ところで、この世の中には、おたがい口にだしていうことをつつしまなければならないことがずいぶんあるものです。取りわけ足に幸福のうわおいぐつなんかはいているときは、たれだって、よけい注意がかんじんです。まあそのとき、夜番の身の上に、どんなことがおこったとおもいますか。
たれしも知っている限りでは、蒸気の物をはこぶ力の早いことはわかっています。それは鉄道でもためしてみたことだし、海の上を汽船でとおってみてもわかります。ところが蒸気の速力などは、光がはこぶ早さにくらべれば、なまけもの[#「なまけもの」に傍点]がのそのそ歩いているか、かたつむりがむずむずはっているようなものです。それは第一流の競走者の千九百万倍もはやく走ります。電気となるともっと早いのです。死ぬというのは電気で心臓を撃たれることなので、その電気のつばさにのって、からだをはなれた魂はとんで行きます。太陽の光は、二千万マイル以上の旅を、八分と二、三秒ですませてしまいます。ところで電気の早飛脚《はやびきゃく》によれば、たましいは、太陽と同じ道のりを、もっと少い時間でとんでいってしまいます。天体と天体とのあいだを往きかいするのは、同じ町のなかで知っている同士が、いやもっと近く、ついお隣同士が往きかいするのと大してちがったことではありません。でも、この下界では心臓を電気にうたれると、からだがはたらかなくなる危険があります。ただこの夜番のように、幸福のうわおいぐつをはいているときだけは、べつでした。
なん秒かで、夜番は五万二千マイルの道をいって、月の世界までとびました。それは、地の上の世界とはちがった、ずっと軽い材料でできていました。そしていわば降りだしたばかりの雪のようにふわふわしています。夜番は例の*メードレル博士の月世界大地図で、あなた方もおなじみの、かずしれず環《わ》なりに取りまわした山のひとつにくだりました。山が輪になってめぐっている内がわに、切っ立てになったはち[#「はち」に傍点]形のくぼみが、なんマイルもふかく掘れていました。その堀の底に町があって、そのようすはちょっというと、卵の白味を、水を入れたコップに落したというおもむきですが、いかにも、さわってみると、まるで卵の白味のように、ぶよぶよやわらかで、人間の世界と同じような塔や、円《まる》屋根のお堂や、帆のかたちした露台《ろだい》が、薄い空気のなかに、すきとおって浮いていました。さて人間の住む地球は、大きな赤黒い火の玉のように、あたまの上の空にぶら下がっていました。
[#ここから5字下げ]
*ドイツの天文学者
[#ここで字下げ終わり]
夜番はまもなく、たくさんの生きものにであいました[#「ました」は底本では「ましだ」]。それはたぶん月の世界の「人間」なのでしょうが、そのようすはわたしたちとはすっかりちがっていました。(**偽《にせ》ヘルシェルが、作り出したものよりも、ずっとたしかな想像でこしらえられていて、一列にならばせて、画にかいたら、こりゃあうつくしいアラビヤ模様だというでしょう。)この人たちもやはり言葉を話しましたが、夜番のたましいにそれがわかろうとは、たれだっておもわなかったでしょう。(ところがそれが、わかったのだからふしぎですが、人間のたましいには、おもいの外の働きがあるのです。そのびっくりするような芝居めいた才能は、夢の中でもはたらくとおりでしょう。そこでは知合のたれかれがでて来て、いかにもその気性をあらわした、めいめい特有《とくゆう》の声で話します。それは目がさめてのちまねようにもまねられないものです。どうしてたましいは、もうなん年もおもいだしもしずにいた人たちを、わたしたちの所へつれてくるのでしょう。それは、わたしたちのたましいのなかへ、いきなりと、ごくこまかいくせまでももってあらわれてきます。まったく、わたしたちのたましいのもつ記憶はおそろしいようですね。それはどんな罪でも、どんなわるいかんがえでも、そのままあらわしてみせます。こうなると、わたしたちの心にうかんで、くちびるにのぼったかぎりの、どんなくだらない言葉でも、そののこらずの明細がきができそうなことです。)
**ドイツで出版された月世界のうそ話。括弧内の文は原本になく、アメリカ版による。
そこで夜番のたましいは、月の世界の人たちの言棄をずいぶんよくときました。その人たちはこの地球の話をして、そこはいったい人間が住めるところかしらとうたぐっていました。なんでも地球は空気が重たすぎて、感じのこまかい月の人にはとても住めまいといいはりました。その人たちは、月の世界だけに人間が住んでいるとおもっているのです。なぜなら、古くからの世界人が住んでいる、ほんとうの世界といったら、月のほかにはないというのです。(この人たちはまた政治の話もしていました。)
それはそれとして、またもとの東通へくだっていって、そこに夜番のたましいがおき去りにして来たからだは、どうしたかみてみましょう。
夜番は、階段の上で息がなくなってねていました。明星《みょうじょう》をあたまにつけたやりは、手からころげ落ちて、その目はぼんやりと月の世界をながめていました。夜番のからだは、そのほうへあこがれてでていった正直なたましいのゆくえをながめていたのです。
「こら夜番、なん時か。」と、往来の男がたずねました。ところが返事のできない夜番でありました。そこでこの男は、ごく軽く夜番の鼻をつつきますと、夜番はからだの平均《へいきん》を失って、ながながと地びたにたおれて、死んでしまいました。鼻をつついた男は、びっくりしたのしないのではありません。夜番が死んだまま生きかえらないのです。さっそく知らせる、相談がはじまる、明くる朝、死体は病院にはこばれました。
ところで、月の世界へあそびにでかけたたましいが、そこへひょっこり帰って来て、東通に残したからだを、ありったけの心あたりを探してみて、みつけなかったら、かなりおもしろいことになるでしょう。たぶんたましいはまず第一に警察へでかけるでしょう。それから人事調査所へもいくでしょう。そしてなくなった品物のゆくえについて捜索《そうさく》がはじまるでしょう。それから、やっと、病院までたずねていくことになるかも知れませんが、でも安心してよろしい。たましいはじぶんの身じんまくをするのは、この上なくきようです。まのぬけているのはからだです。
さて申し上げたとおり、夜番のからだは病院へはこばれました。そうして清潔室《せいけつしつ》に入れられました。死体をきよめるについて、もちろん第一にすることは、うわおいぐつをぬがせることでした。そこで、いやでもたましいはかえってこないわけにはいきません。で、さっそくたましいはからだへもどって来ました。すると、みるみる死骸に気息《いき》がでて来ました。夜番は、これこそ一生に一どの恐しい夜であったと白状しました。もうグロシェン銀貨なん枚もらっても、二どとこんなおもいはしたくないといいました。しかし今となれば、いっさい、すんだことでした。
その日、すぐと、夜番は、病院をでることをゆるされました。けれど、うわおいぐつは、それなり病院にのこっていました。
四 一大事 朗読会の番組 世にもめずらしい旅

コペンハーゲンに生まれたものなら、たれでもその町のフレデリク病院の入口がどんなようすか知っているはずです。でもこの話を読む人のなかには、コペンハーゲン生まれでない人もあるでしょうから、まずそれについて、かんたんなお話をしておかなくてはなりますまい。
さて、その病院と往来とのあいだにはかなり高いさく[#「さく」に傍点]があって、ふとい鉄の棒が、まあ、ずいぶんやせこけた志願助手ででもあったらむりにもぬけられそうな、というくらいの間《ま》をおいて並んでいました。それで、ここからぬけてちょっとしたそとの用事がたせるというわけでした。ただからだのなかで、いちばんむずかしいのはあたまでした。そこでよくあるとおり、ここでも小あたまがなによりのしあわせということになるのでした。まずこのくらいで、前口上はたくさんでしょう。
さて、若いひとりの志願助手がありました。からだのことだけでいうと、大あたまの男でしたが、これが、ちょうどその晩、宿直《しゅくちょく》に当っていました。雨もざんざん降っていました。しかし、このふたつのさわりにはかまわず、この人はぜひそとへでる用がありました。それもほんの十五分ばかりのことだ、門番にたのんで門をあけてもらうまでもなかろう、ついさく[#「さく」に傍点]をくぐってもでられそうだからとおもいました。ふとみると夜番のおいていったうわおいぐつがそこにありました。これが幸福のうわおいぐつであろうとはしりませんでした。こういう雨降りの日には、くっきょうなものがあったとおもって、それをくつの上にはきました。ところで、はたしてさく[#「さく」に傍点]はくぐることができるものかどうか、今までは、ついそれをためしてみたことがないのです、そこでさく[#「さく」に傍点]のまえにたちました、
「どうかあたまがそとにでますように。」と、助手はいいました。するとたちまち、いったいずいぶんのさいづちあたまなのが、わけなくすっぽりでました。そのくらい、うわぐつは心えていました。ところで、こんどはからだをださなければならないのに、そこでぐっとつまってしまいました。
「こりゃ肥りすぎているわい。どうもあたまが一番始末がわるそうだとおもったのだが。でるのはだめか。」と、助手はいいました。
そこで、いそいであたまをひっこめようとしました。けれども、うまくいきませんでした。どうやら動くのは首だけで、しかしそれきりでした。はじめはぷりぷりしてみました。そのうちがっかりして、零下《れいか》何度のごきげんになってしまいました。幸福のうわおいぐつは、この人をこんななさけないめにあわせたのです。しかも、ふしあわせと、ああどうか自由になりたいとひとこということをおもいつかずにいました。そういう代りに、むやみとじれて、がたがたやりました、でもいっこう動けません。雨はしぶきをたててながれました。往来には人ッ子ひとり通りません。門のベルにはせいがとどきません。どうしてぬけだしましょう。こうなると、まずあしたの朝まで、そこにそのままたっているということになりそうです。そこで、みんながみつけてかじ[#「かじ」に傍点]屋を呼びにやってくれて、鉄の格子《こうし》をやすりで切ってだすというところでしょう。だがそういうしごとは、ちょっくりはこぶものではありません。すぐまえの青建物の貧民学校から、総出でくる、すぐそばの海員地区からも、つながってくる、このお仕置台に首をはさまれている、さらし物の見物で、去年|竜舌蘭《りゅうぜつらん》の大輪が咲いたときのさわぎとはまたちがった、大へんな人だかりになるでしょう。
「うう、苦しい。血があたまに上るようだ。おれは気がちがう。――そうだ、もう気がちがいかけている。ああ、どうかして自由になりたい、それだけでもういいんだ。」
これはもう少し早くいえばよかったことでした。こうおもったとおり口にだしたとたん、あたまは自由になりました。幸福のうわおいぐつのおそろしいきき目にびっくりして、助手はむちゅうでうちへかけ込みました。
しかし、これでいっさいすんだとおもってはいけません。これからもっとたいへんなことになるのです。
その晩はそれですぎて、次の日も無事に暮れました。たれもうわおいぐつを取りにくるものはありませんでした。
その日の夕、カニケ街の小さな朗読会の催しがあるはずでした。小屋はぎっしりつまっていました。朗読会の番組のなかに、新作の詩がありました。それをわたしたちもききましょう。さて、その題は、
おばあさんの目がね
ぼくのおばあちゃん、名代《なだい》のもの知り、
「昔の世」ならばさっそく火あぶり、
あったことなら、なんでも知ってて、
その上、来年のことまでわかって、
四十年さきまでみとおしの神わざ、
そのくせ、それをいうのがきらい、
ねえ、来年はどうなりますか、
なにかかわったことでもないか、
お国の大事か、ぼくの身の上、
やっぱり、おばあちゃん、なんにもいわない、
それでもせがむと、おいおいごきげん、
はじめのがんばり、いつものとおりさ、
もうひと押しだ、かわいい孫だ、
ぼくのたのみをきかずにいようか。
「ではいっぺんならかなえてあげる」
やっと承知で目がねを貸した。
「さて、どこなりとおおぜいひとの
あつまるなかへでかけていって
ごったかえしを、目がねでのぞくと、
とたんに、それこそカルタの札の
うらないみたいに、なんでも分かる
さきのさきまで、手にとるように。」
おれいもそこそこ、みたいがさきで、
すぐかけだしたが、さてどこへいく。
長町通《ランケリニエ》か、あそこはさむい、
東堤《エスデルガーデ》か、ペッ、くされ沼
それでは、芝居か、こりゃおもいつき、
出しものもよし――お客は大入。
――そこでまかり出た今夜の催し、
おばばの目がねをまずこうかけて、
さあながめます――お逃けなさるな――
ほんに、皆さま、カルタの札で
未来のうらない、あたればなぐさみ――
ではよろしいか。ご返事ないのは承知のしるし。
さて、ご好意のお礼ごころに、
目がねでみたこと申しあける。
では、皆さまの、じぶんのお国の、未来のひみつ、
カルタのおもてに読みとりまする。
(目がねをかける)
ははん、なるほど、いや、わらわせる。
珍妙《ちんみょう》ふしぎ、お目にかけたい。
カルタの殿方、ずらりとならんで、
お行儀のいい、ハートのご婦人。
そちらに黒いは、クラブにスペード
――ひと目にずんずん、ほら、みえてくる――
スペードの嬢ちゃま、ダイヤのジャックに、
どうやらないしょのうち明け話で、
みているこっちが酔うよなありさま。
そちらはたいしたお金持そうな――
よその国からお客がたえない。
だが、つまらない――どうでもよいこと。
では、政治向。おまちなさいよ――新聞種《しんぶんだね》だ――
のちほどゆっくり読んだらわかるさ。
ここでしゃべると、業務の妨害、
晩のごはんのたのしみなくなる。
そんならお芝居――初演の新作。おこのみ流行。
いけない、これは――支配人とけんかだ。
そこでじぶんの身の上のこと、
たれしもこれが、いちばん気になる。
それはみえます――だがまあいえない、
いずれそのときにゃ、しぜんと分かる。
ここにはいるひと、たれがいちばんしあわせものか。
いちばんしあわせもの。そりゃあ、まあ、わかります。
さようさ、それは――いや、まあ、ごえんりょ申しましょう。
こりゃあ、がっかりなさる方がおおかろう。
では、どなたがいちばん長生きなさるか、
こちらの殿方か、あちらの奥さまか、
いや、こんなこと申さば、なおさらごめいわく。
すると、これか――いや、だめだ――あれか――だめだな、
さあ、あれもと――どうしていいか、さっぱりわからん。
なにしろ、どなたかのごきげんにさわります。
いっそ、皆さまのお心のなか、
それなら目がねも見とおしだ。
皆さん、かんがえていますね。いや、なにかのぞんでおいでかな。
くだらなすぎるというように。
きさま、あんまりばかばかしいぞ、
くだらぬおしゃべりもうやめろ、
それが一致のごいけんならば
はいはいやめます、だまります。
この詩の朗読はなかなかりっぱなできで、演者は面目をほどこしました。見物のなかには、れいの病院の志願助手が、ゆうべの大事件はけろりと忘れたような顔をしてまじっていました。たれも取りにくるものがないので、うわおいぐつは相変らずはいたままでした。それになにしろ往来は道がひどいのでこれはとんだちょうほうでした。
この詩を助手はおもしろいとおもいました。なによりもそのおもいつきが心をひきました。そういう目がねがあったらさぞいいだろう。じょうずにつかうと、その目がねで、ひとの心のなかをみとおすことができるわけだ。これは来年のことを今みるよりも、もっとおもしろいことだとかんがえました。なぜなら、さきのことはさきになれば分かるが、ひとの心なんてめったに分かるものではないのです。
「そこで、おれはまずいちばんまえの紳士貴女諸君の列をながめることにする。――いきなり、あの人たちの胸のなかにとびこんだらどうだろう。まあ窓だな、店をひろげたようにいろいろな物がならんでいるだろう。どんなにおれの目は、その店のなかをきょろきょろすることだろう。きっと、あすこの奥さんの所は大きな小間物屋にはいったようだろう。こちらのほうはきっと店がからっぽだろう。だいぶそうじがとどかないな。だがたしかな品物をうる店だってありそうなものだ。やれやれ。」と、助手はため息をつきながら、またかんがえつづけました。「なんでもたしかな品ばかり売るという店があるのだか、そこにはあいにくもう店番がいる。それがきずさ。こちらの店もあちらの店も「だんな、どうぞおはいりください」といいたそうだ。そこでかわいらしい「かんがえ」の精のようなものになって、あの人たちの胸のなかをのぞきまわってみてやりたい。」
ほら、うわおいぐつにはもうこれだけで通じました。たちまち助手はからだがちぢくれ上がって、一ばんまえがわの見物の心から心へ実にふしぎな旅行をはじめることになりました。まっさきにはいっていったのは、ある奥さまの心で、整形外科《せいけいげか》の手術室にはいりこんだようにおもいました。これはお医者さまが、かたわな人のよぶんな肉を切りとって、からだのかっこうをよくしてくれる所をいうのです。そのへやには、かたわな手足のギプス型が壁に立てかけてありました。ただちがうのは整形病院では、ギプス型を患者《かんじゃ》がはいってくるたんびにとるのですが、この心のなかでは、人がでていったあとで型をとって、保存されることでした。ここにあるのは女のお友だちの型で。そのからだと心の欠点がそのままここに保存されていました。
すぐまた、ほかの女のなかにはいっていきました。しかし、これは大きな神神《こうごう》しいお寺のようにおもわれました。無垢《むく》の白はとが、高い聖壇の上をとんでいました。よっぽどひざをついて拝みたいとおもったくらいでした。しかし、すぐと次の心のなかにはいっていかなければなりませんでした。でも、まだオルガンの音がきこえていました。そうしてじぶんがまえよりもいい、別の人間になったようにおもわれました。いばって次の聖堂にはいる資格が、できたように感じました。それは貧しい屋根裏のへやのかたちであらわれて、なかには病人のおかあさんがねていました。けれどあいた窓からは神さまのお日さまの光が温かくさしこみましたうつくしいばらの花が、屋根の上の小さな木箱のなかから、がてんがてん[#「がてんがてん」に傍点]していました。空色した二羽の小鳥が、こどもらしいよろこびのうたを歌っていました。そのなかで、病人のおかあさんは、むすめのために、神さまのおめぐみを祈っていました。
それから、肉でいっぱいつまった肉屋の店を、四つんばいになってはいあるきました。ここは肉ばかりでした。どこまでいっても、肉のほかなにもありませんでした。これはお金持のりっぱな紳士《しんし》の心でした。おそらく、この人の名まえは紳士録にのっているでしょう。
こんどはその紳士の奥さまの心のなかにはいりました。その心は、古い荒れはてたはと小屋でした。ごていしゅの像がほんの風見《かざみ》のにわとり代りにつかわれていました。その風見は、小屋の戸にくっついていて、ごていしゅの風見がくるりくるりするとおりに、あいたりとじたりしました。
それからつぎには、ローゼンボルのお城でみるような鏡の間《ま》にでました。でもこの鏡は、うそらしいほど大きくみせるようにできていました。床《ゆか》のまんなかには、達頼喇嘛《ダライラマ》のように、その持主のつまらない「わたし」が、じぶんでじぶんの家の大きいのにあきれながらすわっていました。
それからこんどは、針がいっぱいつんつんつッたっている、せまい針箱のなかにはこばれました。これはきっと年をとっておよめにいけないむすめの心にちがいないとおもいました。けれど、じつはそうではありません。たくさん勲章をぶら下げている若い士官の心でした。しかし、世間ではこの人を才と情のかねそなわった人物だといっていました。
あわれな助手は、列のいちばんおしまいの人の心からぬけだしたとき、すっかりあたまがへんになっていて、まるでかんがえがまとまりませんでした。やたらとはげしいもうぞう[#「もうぞう」に傍点]が、じぶんといっしょにかけずりまわったのだとおもいました。
「やれやれ、おどろいた。」と、助手はため[#「ため」に傍点]息をつきました。「おれはどうも気ちがいになるうまれつきらしい。それに、ここは、むやみと暑い。血があたまにのぼるわけさ。」
そこで、ふとゆうべの、病院の鉄さくにあたまをはさまれた大事件をおもいだしました。
「きっとあのとき病気にかかったにちがいない。」と、助手はおもいました。「すぐどうかしなければならない。ロシア風呂《ぶろ》がきくかも知れない。ならば一等上のたなにねたいものだ。」
するともう、さっそくに蒸風呂《むしぶろ》のいちばん上のたなにねていました。ところで、着物を着たなり、長ぐつも、うわおいぐつもそのままでねていました。天井《てんじょう》からあついしずくが、ぽた、ぽた、顔に落ちて来ました。
「うわあ。」と、とんきょうにさけんで、こんどは灌水浴《かんすいよく》をするつもりで下へおりました。
湯番は着物を着こんだ男がとびだしたのをみてびっくりして、大きなさけび声をたてました。
でも、そういうなか[#「なか」は底本では「な声」]で、助手は、湯番の耳に、
「なあにかけ[#「かけ」に傍点]をしているのだよ。」と、ささやくだけの余裕《よゆう》がありました。さて、へやにかえってさっそくにしたことは、首にひとつ、背中にひとつ、大きなスペイン発泡膏《はっぽうこう》をはることでした。これでからだのなかの気ちがいじみた毒気を吸いとろうというわけです。
明くる朝、助手は、赤ただれたせなかを[#「せなかを」は底本では「せなをか」]していました。これが幸福のうわおいぐつからさずけてもらった御利益《ごりやく》のいっさいでした。
五 書記の変化《へんげ》
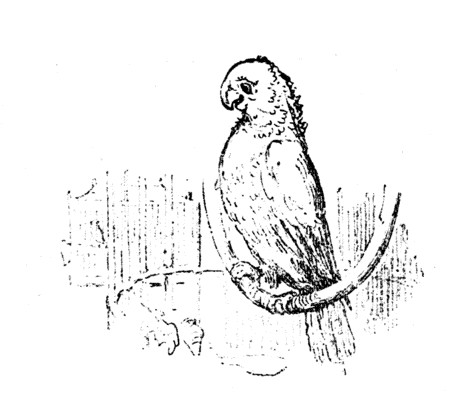
さて、わたしたちがまだ忘れずにいたあの夜番は、そのうち、じぶんがみつけて、病院までもはいていったうわおいぐつのことをおもいだしました。そこで、とってかえりましたが、むこう二階の中尉にも、町のたれかれにきいても、持主は、わかりませんでしたから、警察へとどけました。
「これはわたしのうわおいぐつにそっくりだ。」と、この拾得物《しゅうとくぶつ》をみた書記君のひとりがいって、じぶんのと並べてみました。「どうして、くつ屋でもこれをみわけるのはむずかしかろう。」
「書記さん。」と、そのとき小使が書類をもってはいって来ました。
書記はふりむいてその男と話をしていました。話がすむと、またうわおいぐつのほうへむかいましたが、もうそのときは、右か左かじぶんのがわからなくなってしまいました。
「しめっているほうがわたしのにちがいない。」と、書記君はおもいました。でも、これはかんがえちがいでした。なぜなら、そのほうが幸福のうわおいぐつだったのです。だって警察のお役人だって、まちがわないとはかぎらないでしょう。で、すましてそれをはいて、書類をかくしにつッこみました。それからあとは小わきにかかえました。これを内へかえって読んで、コピイ(副本)をつくらなければならないのです。ところで、その日は日曜の朝で、いいお天気でした。ひとつ、フレデリクスベルグへでもぶらぶらでてみるかな、とかんがえて、そちらに足をむけました。
さて、この青年ぐらい、おとなしい、堅人《かたじん》はめったにありません。すこしばかりの散歩を、この人がするのは、さんせいですよ。ながく腰をかけ通していたあとで、きっとからだにいいでしょう。はじめのうち、この人もただぽかんとしてあるいていました。そこで、うわおいぐつも魔法をつかう機会がありませんでした。
公園の並木道《なみきみち》にはいると、書記はふとお友だちの、若い詩人にであいました。詩人は、あしたから旅にでかけるところだと話しました。
「じゃあ、もうでかけるのかい。」と、書記はうらやましそうにいいました。「なんて幸福な自由な身の上だろう。いつどこへでも、好きなところへとんでいけるのだ。われわれと来ては、足にくさりをつけられているのだからね。」
「だが、そのくさりはパンの木にゆいつけてあるのだろう。」と、詩人はいいました。「そのかわりくらしの心配はいらないのだ。年をとれば、恩給がもらえるしな。」
「やはりなんといっても、きみのほうがいいくらしをしているよ。」と、書記がいいました。「うちにすわって詩を書いているというのは、楽しみにちがいない。それで世間からはもてはやされる。おれはおれだでやっていける。まあ、きみ、いちどためしにやってみたまえ。こまごました役所のしごとに首をつっこんでいるということが、どんなことだかわかるから。」
詩人はあたまをふりました。書記も同様にあたまをふりました。てんでにじぶんじぶんの意見をいい張って、そのままふたりは別れました。
「どうも詩人というものはきみょうななかまだな。」と、書記はおもいました。「わたしもああいう人間の心持になってみたいものだ。じぶんで詩人になってみたいものだ。わたしなら、むろん、あの連中のように泣言をならべはしないぞ……ああ、詩人にとってなんてすばらしい春だろう。あんなにも空気は澄み、雲はあくまでうつくしい。わか葉の緑にかおりただよう。そうだ、もうなん年にも、このしゅんかんのような気持をわたしは知らなかった。」
これで、もうこの書記は、さっそく、詩人になっていたことがわかります。べつだん目につくほどのことはありません。いったい詩人とほかの人間とでは、うまれつきからまるでちがっているようにかんがえるのは、ばかげたことです。ただの人で詩人と名のっているたいていの人間よりも、もっと詩人らしい気質の人がいくらもあるのです。ただまあ詩人となれば、おもったこと感じたことをよくおぼえていて、それをはっきりと、言葉に書きあらわすだけの天分がある、そこらがちがうところです。でも、世間なみの気質から詩人の天分にうつるというのは、やはり大きなかわり方にちがいないので、それをいま、この書記君がしているのです。
「なんとすばらしい匂だ。」と、書記はいいました。「ローネおばさんのすみれの花をおもい出させる。そう、あれはわたしのこどものじぶんだった。はてね、ながいあいだおもいだしもしずにいたのだがな。いいおばさんだったなあ。おばさんは取引所のうしろに住んでいた。いつも木の枝か青いわか枝をだいじそうに水にさして、どんな冬の寒いときでも、あたたかいへやのなかにおいた。ほっこりとすみれが花をひらいているわきで、わたしは凍った窓ガラスに火であつくした銅貨をおしつけて、すきみの穴をこしらえたものだ。あれはおもしろい見物だった。そとの掘割には船が氷にとじられていた。乗組はみんなどこかへいっていて、からすが一羽のこってかあかあないていた。やがて春風がそよそよ吹きそめると、なにかが生き生きして来た。にぎやかな歌とさけび声のなかに、氷がこわされる。船にタールがぬられて、帆綱のしたくができると、やがて知らない国へこぎ出していってしまう。でも、わたしはいつまでもここにのこっている。年がら年じゅう警察のいすに腰をかけて、ひとが外国行の旅券を受け取っていくのをながめている、これがわたしの持ってうまれた運なのだ。うん、うん、どうも。」
こうおもって、書記はふかいため息をつきましたが。ふと、気がついて、
「はて、おかしいぞ。わたしは、いったいどうしたというのだろう。いつもこんなふうに、かんがえたり感じたりしたことはなかったのに。きっと心のなかに春風が吹き込んだのかな。なにかやるせないようで、そのくせいい気持だ。」
こうおもいながらなにげなくかくし[#「かくし」に傍点]のなかの紙に手をふれました。「いけない。これがせっかくのかんがえをほかにむけさせるのだ。」書記はそういいながらはじめの一枚にふと目をさらしますと、それはこう読まれました。「『ジグブリット夫人、五幕新作悲劇』おやおや、これはなんだ。しかもこれはわたしの手だぞ。わたしはいつこんな悲劇《ひげき》なんて書いたろう。軽喜歌劇散歩道の陰謀 一名懺悔祈祷日。はてね、どこでこんなものをもらったろう。たれかいたずらに、かくしに入れたかな。おやおや、ここに手紙があるぞ。」
いかにもそれは劇場の支配人から来たものでした。あなたのお作は上場いたしかねますと、それもいっこう礼をつくさない書きぶりで書いてありました。
「ふん、ふん。」こう書記はつぶやきながら、腰掛に腰をおろしました。なにか心がおどって、生きかえったようで、気分がやさしくなりました。ついすぐそばの花をひとつ手につみました。それはつまらない、ちいさなひなぎくの花でした。植物学者が、なんべんも、なんべんも、[#「、」は底本では「。」]お講義を重ねて、やっと説明することを、この花はほんの一分間に話してくれました。それはじぶんの生いたちの昔話もしました。お日さまの光がやわらかな花びらをひらかせ、いい匂を立たせてくださる話もしました。そのとき、書記は、「いのちのたたかい」ということを、ふとおもいました。これもやはりわたしたちの心を動かすものでした。
空気と光は花と仲よしでした。それでも光がよけいすきなので、いつも光のほうへ、花は顔をむけました。ただ光が消えてしまったとき、花は花びらをまるめて、空気に抱かれながら眠りました。
「わたしを飾ってくれるのは、光ですよ。」と、花はいいました。
「でも、空気はおまえに息をさせてくれるだろう。」と、詩人の声がささやきました。
すると、すぐそばに、ひとりの男の子が、溝川《どぶかわ》の上を棒でたたいていました。にごった水のしずくが緑の枝の上にはねあがりました。すると、書記はそのしずくといっしょにたかく投げあげられたなん万という目にみえないちいさい生き物のことをおもいました。それは、からだの大きさの割合からすると、ちょうどわたしたちが雲の上まで高く投げられたと同じようなものでしょうか。そんなことを書記はおもいながら、だんだんかわっていくじぶんをおかしく感じました。
「どうも眠って夢をみているのだな。だが、ふしぎなことにはちがいない。そんなにまざまざ夢をみていて、しかも夢のなかで、それが夢だと知っているのだからな。どうかして夢にみたことをのこらず、あくる日目がさめてもおぼえていられたらいいだろう。どうもいつもとちがって、気分がみょうにうかれている。なにをみてもはっきりわかるし、生き生きとものをかんじている。でも、あしたになっておもいだしたら、ずいぶんばかげているにちがいない。せんにもよくあったことだ。夢のなかでいろいろと賢いことやりっぱなことをいったり、きいたりするものだ。それは地の下の小人《こびと》の金《きん》のようなものだ。それを受けとったときには、たくさんできれいな金にみえるが、あかるい所でみると、石ころか枯ッ葉になってしまう。やれ、やれ。」
書記は、さもつまらなそうにため[#「ため」に傍点]息をついて、枝から枝へ、愉快そうにとびまわって、ちいちいさえずっている小鳥をながめました。
「小鳥はわたしよりずっとよくくらしている。とぶということは、なにしろたいしたわざだ。つばさをそなえてうまれたものはしあわせだ。そうだな。わたしがもしなにか人間でないものに変れるならかわいいひばりになりたいものだ。」
こういうが早いか、書記の服のせなかに、両そでがびったりくっついて、つばさになりました。着物は羽根になり、うわおいぐつはつめ[#「つめ」に傍点]になりました。書記はじぶんのずんずん変っていくすがたをはっきりみながら、心のなかでわらいました。「なるほど、これでいよいよ夢をみていることがわかる。だが、わたしはまだこんなおもいきってばかげた夢をみたことはないぞ。」こういって、ひばりになった書記は、みどりの枝のなかをとびまわってうたいました。
もう、その歌に詩はありません。詩人の気質はなくなってしまったのです。このうわおいぐつは、なんでもものごとをつきつめてするひとのように、一時じ》にひとつのことしかできません。詩人になりたいというと、詩人になりました。こんどは小鳥になりたいというと、小鳥になりました。とたんに詩人の心は消えました。
「こいつは実におもしろいぞ。」と、書記はとびながら、なおかんがえつづけました。「わたしは昼間、役所につとめて、石のように堅い椅子に腰をかけて、おもしろくないといって、およそこの上ない法律書類のなかに首をつッこんでいる。夜になると夢をみて、ひばりになって、フレデリクスベルグ公園の木のなかをとびまわる。こりゃあ、りっぱに大衆喜劇の種《たね》になる。」
そこで、書記のひばりは草のなか[#「なか」は底本では「なが」]に舞いおりて、ほうぼうに首をむけて、草の茎をくちばしでつつきました。それはいまのじぶんの大きさにくらべては、北アフリカのしゅろ[#「しゅろ」に傍点]の枝ほどもありそうでした。
すると、だしぬけにまわりがまっ暗やみになってしまいました。なにか大きなものが、上からかぶさって来たようにおもわれました。これはニュウボデルから来た船員のこどもが、大きな帽子を小鳥の上に投げかけたものでした。やがて下からぬっ[と手がはいって来て、書記のひばりのせなかとつばさをひどくしめつけたので、おもわずぴいぴい鳴きました。そして、びっくりした大きな声で「このわんぱく小僧め、おれは警察のお役人だぞ。」とどなりました。けれどもこどもには、ただぴいぴいときこえるだけでした。そこでこの男の子は鳥のくちばしをたたいて、つかんだままほうぼうあるきまわりました。
やがて、並木道《なみきみち》で、男の子はほかのふたりのこどもに出あいました。身分をいう人間の社会では、いい所のこどもというのですが、学校では精紳がものをいうので、ごく下の級に入れられていました。このこどもたちが、シリング銀貨二、三枚で小鳥を買いました。そこで、ひばりの書記は、またコペンハーゲンのゴーテルス通のある家へつれてこられることになりました。
「夢だからいいようなものだが。」と、書記はいいました。「さもなければ、おれはほんとうにおこってしまう。はじめに詩人で、こんどはひばりか。しかもわたしを小鳥にかえたのは、詩人の気質がそうしたのだよ。それがこどもらの手につかまれるようになっては、いかにもなさけない。このおしまいは、いったいどうなるつもりか、見当がつかない。」
やがて、こどもたちはひばりをたいそうりっぱなおへやにつれこみました。ふとったにこにこした奥さまが、こどもたちをむかえました。この子たちのおかあさまでしたろう。けれども、このおかあさまは、ひばりのことを「下等な野そだちの鳥」とよんで、そんなものをうちのなかへ入れることをなかなかしょうちしてくれません。やっとたのんで、ではきょう一日だけということで許してもらえました。で、ひばりは窓のわきにある、からッぽなかごのなかに入れられなければなりませんでした。「おうむちゃん、きっと、うれしがるでしょうよ。」と、奥さまはいって、上のきれいなしんちゅうのかごのなかの輪で、お上品ぶってゆらゆらしている大きなおうむにわらいかけました。
「きょうはおうむちゃんのお誕生日だったねえ。」と、奥さまはあまやかすようにいいました。「だから、このちっぽけな野そだちの鳥もお祝をいいに来たのだろうよ。」
おうむちゃんはこれにひとことも返事をしませんでした。ただお上品ぶってゆらゆらしていました。すると、去年の夏、あたたかい南の国のかんばしい林のなかから、ここへつれてこられた、かわいらしいカナリヤが、たかい声で歌をうたいはじめました。
「やかましいよ。」と、奥さまはいいました。そうして白いハンケチを鳥かごにかけてしまいました。
「ぴい、ぴい。」と、カナリヤはため息をつきました。「おそろしい雪おろしになって来たぞ。」こういってため息をつきながら、だまってしまいました。
書記は、いや、奥さまのおっしゃる下等な野そだちの鳥は、カナリヤのすぐそばのちいさなかごに入れられました。おうむからもそう遠くはなれてはいませんでした。このおうむちゃんのしゃべれる人間のせりふはたったひとつきり、それは、「まあ、人になることですよ。」というので、それがずいぶんとぼけてきこえるときがありました。そのほかに、ぎゃあぎゃあいうことは、カナリヤの歌と同様、人間がきいてもまるでわけがわかりませんでした。ただ書記だけは、やはり小鳥のなかまにはいったので、いうことはよくわかりました。
「わたしはみどりのしゅろ[#「しゅろ」に傍点]の木や、白い花の咲くあんず[#「あんず」に傍点]の木の下をとんでいたのだ。」と、カナリヤがうたいました。「わたしは男のきょうだいや女のきょうだいたちと、きれいな花の咲いた上や、鏡のようにあかるいみどりの上をとんでいたのだ。みずうみの底には、やはり草や木が、ゆらゆらゆられていた。それからずいぶん、ながいお話をたくさんしてくれるきれいなおうむさんにもあった。」
「ありゃ野そだちの鳥よ。」と、おうむがこたえました。「あれらはなにも教育がないのだ。まあ人になることですよ。おまえ、なぜわらわない。奥さんやお客さんたちがわらったら、おまえもわらう。娯楽に趣味をもたないのは欠点です。まあ人になることですよ。」
「おまえさん、おぼえているでしょう。花の咲いた木の下に、天幕を張って、ダンスをしたかわいらしいむすめたちのことを、野に生えた草のなかに、あまい実がなって、つめたい汁の流れていたことを。」
「うん、そりゃ、おぼえている。」と、おうむがこたえました。「だが、ここのお内で、ぼくはもっといいくらしをしているのだ。ごちそうはあるし、だいじに扱われている。この上ののぞみはないのさ。まあ、人になることですよ。きみは詩人のたましいとかいうやつをもっている。ぼくはなんでも深い知識ととんちをもっている。きみは天才はあるが、思慮《しりょ》がないよ。持ってうまれた高調子で、とんきょうにやりだす、すぐ上からふろしきをかぶされてしまうのさ。そこはぼくになるとちがう。どうしてそんな安ッぽいのじゃない。この大きなくちばしだけでも、威厳《いげん》があるからな。しかもこのくちばしで、とんち[#「とんち」に傍点]をふりまいて人をうれしがらせる。まあ、人になることですよ。」
「ああ、わがなつかしき、花さく熱帯の故国よ。」とカナリヤがうたいました。「わたしはあのみどりしたたる木立と、鏡のような水に枝が影をうつしている静かな入江をほめたたえよう。『沙漠《さばく》の泉の木』が茂って、そこにうつくしくかがやくきょうだいの鳥たちのよろこびをほめたたえよう。」
「さあ、たのむから、もうそんななさけない声を出すのはよしておくれ。」と、おうむがいいました。
「なにかわらえるようなことをうたっておくれ。わらいはいとも高尚な心のしるしだ。犬や馬がわらえるかね。どうだ。どうして、あれらはなくだけです。わらいは人にだけ与えられたものだ。ほッほッほ。」
こうおうむはわらってみせて、「まあ、人になることですよ。」とむすびました。
「もし、もし、そこに灰色しているデンマルクの小鳥さん。」と、カナリヤがひばりに声をかけました。「きみもやはり囚人《しゅうじん》になったんだな。なるほど、きみの国の森は寒いだろう。だが、そこにはまだ自由がある。とびだせ。とびだせ。きみのかごの戸はしめるのを忘れている。上の窓はあいているぞ。逃げろ、逃げろ。」
カナリヤがこういうと、書記はついそれにのって、すうとかどをとびだしました。そのとたん、となりのへやの、半分あいた戸がぎいと鳴ると、みどり色した火のような目の飼いねこがしのんで来ました。そうして、いきなりひばりを追っかけようとしました、カナリヤはかごのなかをとびまわりました。おうむもつばさをばさばさやって「まあ、人になることですよ。」とさけびました。書記は、もう死ぬほどおどろいて、窓から屋根へ往来へとにげました。とうとうくたびれて、すこし休まなければならなくなりました。
すると、むこうがわの家が、住み心地のよさそうなようすをしていました。窓がひとつあけてあったので、[#「、」は底本では「。」]そこからつういととび込むと、そこはじぶんのへやの書斎でした。ひばりはそこのつくえの上にとびおりました。
「まあ、人になることですよ。」と、ひばりはついおうむの口まねをしていいました。そのとたんに、書記にもどりました。ただつくえの上にのっかっていました。
「やれ、やれおどろいた。」と、書記はいいました。「どうしてこんな所にのっかっているのだろう。しかもひどく寝込んでしまって、なにしろおちつかない夢だった。しまいまで、くだらないことばかりで、じょうだんにもほどがある。」
六 うわおいぐつのさずけてくれたいちばんいい事
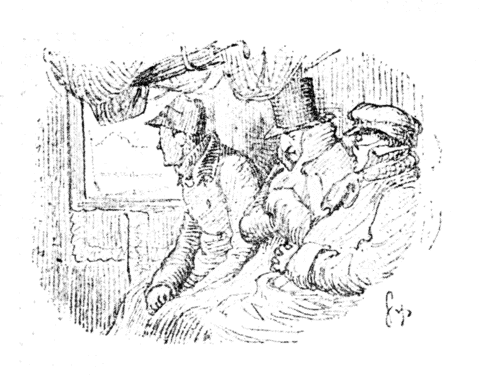
明くる日、朝早く、書記君まだ寝床にはいっていますと、戸をこつこつやる音がきこえました。それはおなじ階でおとなり同士の若い神学生で、はいって来てこういいました。
「きみのうわおいぐつを貸してくれたまえ。」と、学生はいいました。「庭はひどくしめっているけれど、日はかんかん照っている。おりていって、一服やりたいとおもうのだよ。」
学生にうわおいぐつをはいて、まもなく庭へおりました。庭にはすももの木となしの木がありました。これだけのちょっとした庭でも、都のなかではどうして大したねうちです。
学生は庭の小みちをあちこちあるきまわりました。まだやっと六時で、往来には郵便馬車のラッパがきこえました。
「ああ、旅行。旅行。」と、学生はさけびました。「これこそ、この世のいちばん大きな幸福だ。これこそぼくの希望のいちばんたかい目標だ。旅に出てこそぼくのこの不安な気持が落ちつく、だが、ずっととおくではなければなるまい。うつくしいスウィスがみたい。イタリアへいきたい――」
いや、うわおいぐつがさっそくしるしをみせてくれたことは有りがたいことでした。さもないと、じぶんにしても、他人のわたしたちにしても、始末のわるい遠方までとんでいってしまうところでした。さて、学生は旅行の途中です。スウィスのまんなかで、急行馬車に、ほかの八人の相客といっしょにつめこまれていました。頭痛がして、首がだるくて、足は血が下がってふくれた上をきゅうくつな長ぐつでしめつけられていました。眠っているとも、さめているともつかず、うとうとゆられていました。右のかくしには信用手形を入れ、左のかくしには、旅券を入れていました。ルイドール金貨が胸の小さな革紙入にぬい入れてありました。うとうとするとこのだいじな品物のうちどれかをなくした夢をみました。それで、熱のたかいときのように、ひょいととびあがりました。そうしてすぐと手を動かして、右から左へ三角をこしらえて、それから胸にさわってまだなくさずに持っているかどうかみました。こうもりがさと帽子とステッキは、あたまの上の網のなかでゆれてぶら下がっていて、せっかくのすばらしいそとの景色をみるじゃまをしていました。でも、その下からのぞいてみるだけでして、そのかわり学生は心のなかで、詩人とまあいってもいいでしょう、わたしたち知っているさる人が、スウィスで作って、そのまままだ印刷されずにいる詩をうたっていました。
さなり、ここに心ゆくかぎりの美はひらかれ
モンブランの山|天《あま》そそる姿をあらわす。
嚢中《のうちゅう》のかくもすみやかに空しからずば、はや
あわれ、いつまでもこの景にむかいいたらまし。
みるかぎりの自然に、大きく、おごそかで、うすぐらくもみえました。もみの木の林が、高い山の上で、草やぶかなんぞのようにみえました。山のいただきは雲霧《くもきり》にかくれてみえませんでした。やがて雪が降りはじめて、風がつめたく吹いて来ました。
「おお、寒い。」と、学生はため息をつきました。「これがアルプスのむこうがわであったらいいな。あちらはいつも夏景色で、その上、この信用手形でお金が取れるのだろうが。金の心配で、せっかくのスウィスも十分に楽しめない。どうかはやくむこうへいきたいなあ。」
こういうと、もう学生は山のむこうがわのイタリアのまんなかの、フィレンツェとローマのあいだに来ていました。トラジメーネのみずうみは、夕ばえのなかで、暗いあい色の山にかこまれながら、金色のほのおのようにかがやいていました。ここは昔、ハンニバルがフラミウスをやぶったところで、そこにぶどうのつるが、みどりの指をやさしくからみあっていました。かわいらしい半裸体のこどもらが、道ばたの香り高い月桂樹《げっけいじゅ》の林のなかで、まっ黒なぶたの群を飼っていました。もしこの景色をそのまま画にかいてみせることができたら、たれだって「ああ、すばらしいイタリア。」とさけばずにはいられないでしょう。けれどもさしあたり神学生も、おなじウェッツラ(四輪馬車)にのりあわせた旅の道づれも、それをくちびるにのせたものはありませんでした。
毒のあるはえ[#「はえ」に傍点]やあぶ[#「あぶ」に傍点]が、なん千となく、むれて馬車のなかへとびこんで来ました。みんな気ちがいのように、ミルテの枝をふりまわしましたが、はえ[#「はえ」に傍点]はへいきで刺しました。馬車の客は、ひとりだってさされて顔のはれあがらないものはありませんでした。かわいそうな馬は腐れ肉でもあるかのようにはえ[#「はえ」に傍点]のたかるままになっていました。たまにぎょ[#「ぎょ」に傍点]者がおりて、いっぱいたかっている虫をはらいのけると、そのときだけいくらかほっとしました。いま、日は沈みかけました。みじかい、あいだですが、氷のような冷やかさが万物にしみとおって、それはどうにもこころよいものではありません。でも、まわりの山や雲が、むかしの画にあるような、それはうつくしいみどり色の調子をたたえて、いかにもあかるくすみとおって――まあなんでも、じぶんでいってみることで、書いたものをよむだけではわかりません。まったくたとえようのないけしきです。この旅行者たちたれもやはりそうおもいました。でも――胃《い》の腑《ふ》はからになっていましたし、からだも疲れきっていました。ただもう今夜のとまり、それだけがたれしもの心のねがいでした。さてどうそれがなるのか。うつくしい自然よりも、そのほうへたれの心もむかっていました。
道は、かんらんの林のなかを通っていきました。学生は、故郷にいて、節だらけのやなぎの木のあいだをぬけて行くときのような気もちでした。やがてそこにさびしい宿屋をみつけました。足なえのこじきがひとかたまり、そこの入口に陣取っていました。なかでいちばんす早いやつでも、ききんの惣領《そうりょう》息子が丁年になったような顔をしています。そのほかは、めくらかいざり[#「いざり」に傍点]かどちらかでしたから、両手ではいまわるか、指の腐れおちた手をあわせていました。これはまったくみじめ[#「みじめ」に傍点]がぼろにくるまって出て来た有様でした。*「エチェレンツア・ミゼラビリ」と、こじきはため息まじりにかたわな手をさしだしました。なにしろこの宿屋のおかみさんからして、はだしでくしを入れないぼやぼやのあたまに、よごれくさったブルーズ一枚でお客を迎えました。戸はひもでくくりつけてありました。へやのゆかは煉瓦《れんが》が半分くずれた上を掘りかえしたようなていさいでした。こうもりが天井《てんじょう》の下をとびまわって、へやのなかから、むっとくさいにおいがしました――。
[#ここから5字下げ]
*旦那さま、かわいそうなものでございます。
[#ここで字下げ終わり]
「そうだ、いっそ食卓はうまやのなかにもちだすがいい。」と、旅人のひとりがいいました。「まだしもあそこなら息ができそうだ。」
窓はあけはなされました。そうすればすこしはすずしい風がはいってくるかとおもったのです。ところが風よりももっとす早く、かったい[#「かったい」に傍点]ぼうの手がでて来て、相変らず「ミゼラビリ・エチェレンツア」と鼻をならしつづけました。壁のうえにはたくさん楽書《らくがき》がしてありましたが、その半分は*「ベルラ・イタリア」にはんたいなことばばかりでした。
[#ここから5字下げ]
*イタリアよいとこ。
[#ここで字下げ終わり]
夕飯がでました。それはこしょうと、ぷんとくさい脂で味をつけた水っぽいスープとでした。そのくさい脂がサラダのおもな味でした。かびくさい卵と、鶏冠《とさか》の焼いたのが一とうのごちそうでした。ぶどう酒《しゅ》までがへんな味がしました。それはたまらないまぜものがしてありました。
夜になると、旅かばんをならべて戸に寄せかけました。ほかのもののねているあいだ、旅人のひとりが交代で起きて夜番をすることになりました。そこで神学生がまずその役にあたりました。ああ、なんてむんむすることか。暑さに息がふさがるようでした。蚊《か》がぶん、ぶん、とんで来て刺しました。おもての「ミゼラビリ」は夢のなかでも泣きつづけていました。
「そりゃ旅行もけっこうなものさ。」と、神学生はいいました。「人間に肉体というものがなければな。からだは休ましておいて、心だけとびあるくことができたらいいさ。どこへいってもぼくは心をおされるよう不満にであう。ぼく[#「ぼく」は底本では「くぼ」]ののぞんでいたのは、現在の境遇より少しはいいものなのだ。そうだ、もう少しいいもの、いちばんいいものだ。だが、それはどこにある。それはなんだ。心のそこには求めているものがなにかよくわかっている。わたしは幸福を目あてにしたいのだ。すべてのもののなかでいちばん幸福なものをね。」
すると、いうがはやいか、学生は、もうじぶんの内へかえっていました、長い、白いカーテンが窓からさがっていました。そうしてへやのまんなかに、黒い棺《かん》がおいてありました。そのなかで、学生は死んで、しずかに眠っていたのでした。のぞみははたされたのです――肉体は休息して、精神だけが自由に旅をしていました。「いまだ墓にいらざるまえ、なにびとも幸福というを得ず。」とは、ギリシアの賢人ソロンの言葉でした。ここにそのことばが新しく証明されたわけです。
すべて、しかばねは不死不滅のスフィンクスです。いま目のまえの黒い棺《かん》のなかにあるスフィンクスも、死ぬつい三日まえ書いた、次のことばでそのこたえをあたえているのです。
いかめしい死よ、おまえの沈黙は恐怖をさそう。
おまえの地上にのこす痕跡《あと》は寺の墓場だけなのか。
たましいは*ヤコブのはしごを見ることはないのか。
墓場の草となるほかに復活の道はないのか。
この上なく深いかなしみをも世間はしばしばみすごしている。
おまえは孤独のまま最後の道をたどっていく。
しかもこの世にあって心の荷《にな》う義務はいやが上に重い、
それは棺の壁をおす土よりも重いのだ。
* ヤコブがみたという地上と天国をつなぐはしご(創世記二八ノ一二)
ふたつの姿がへやのなかでちらちら動いていました。わたしたちはふたりとも知っています。それは心配の妖女《ようじょ》と、幸福の女神の召使でした。ふたりは死人の上にのぞきこみました。
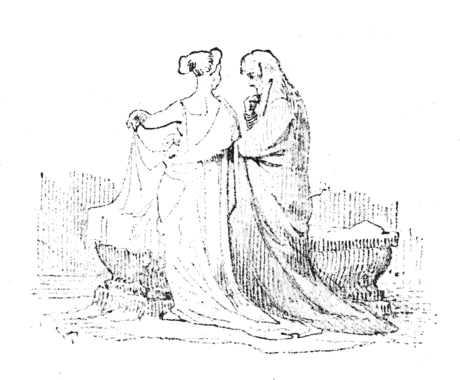
心配がいいました。「ごらん、おまえさんのうわおいぐつがどんな幸福をさずけたでしょう。」
「でも、とにかくここに寝ている男には、ながい善福をさずけたではありませんか。」と、よろこびがこたえました。
「まあ、どうして。」と、心配がいいました。「この人はじぶんで出て行ったので、まだ召されたわけではなかったのですよ。この人の精神はまだ強さが足りないので、当然掘り起さなければならないはずの宝を掘り起さずにしまいました。わたしはこの人に好いことをしてやりましょう。」
こういって、心配は学生の足のうわおいぐつをぬがしてやりました。すると、死の眠がおしまいになって、学生は目をさまして立ちあがりました。心配の姿は消えました。それといっしょにうわおいぐつも消えてなくなりました。――きっと心配が、そののちそれをじぶんの物にして、もっているのでしょう。
底本:「新訳アンデルセン童話集第一巻」同和春秋社
1955(昭和30)年7月20日初版発行
※「旧字、旧仮名で書かれた作品を、現代表記にあらためる際の作業指針」に基づいて、底本の表記をあらためました。
※底本中、*で示された語句の訳註は、当該語句のあるページの下部に挿入されていますが、このファイルでは当該語句のある段落のあとに、5字下げで挿入しました。
※疑問箇所の確認にあたっては、「アンデルセン童話集2 一本足の兵隊」冨山房百科文庫、冨山房、1938(昭和13)年12月10日発行を参照しました。
入力:大久保ゆう
校正:秋鹿
2006年1月18日作成
2009年9月13日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。


コメント